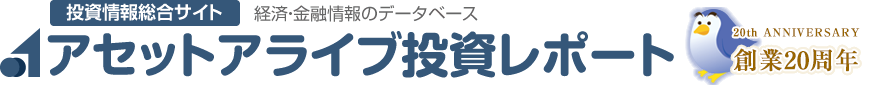再生医療や難病の研究で各地の大学が連携している。
安全性の高い細胞を作製・培養できる設備を持つ大学は限られている。再生医療では、医療機関は患者から採取した細胞をもとにiPS細胞などを作り移植を行うが、専用設備や管理などで費用がかさむからだ。
そのため、これらの設備を持つ大学と組む動きが出ている。
慶應大学では、自治医大から緊縮性側索硬化症(ALS)やパーキンソン病など神経の難病患者の皮膚などを受取、iPS細胞に変える。この細胞を使い自治医大が治療法を突き止めるという協力関係を構築している。
また、京都大学ではiPS細胞を使い、筋細胞が痛んで歩きにくくなる菌疾患の治療薬開発で東北大学と協力するようだ。
再生医療研究で知られる慶應大学や京都大学が、厚生労働省の難病研究班に加わる大学と連携し、数年以内に新薬の候補物質を見つけたい考え。
---
【再生医療連携】
・大阪市立大学や兵庫医大など8機関 幹細胞を注射して軟骨の再生へ取組。大阪大学で増やした細胞を移植。2013年度臨床研究開始。
投資に関する金融市場動向や経済動向のレポートを発信。
- 新着情報
-
- 3月22日【脊髄損傷】
- 5月29日【GDP】各国のGDP推移 2020年
- 5月29日【政策金利推移】2020年
- 5月29日【新型コロナ】第2次補正予算案
- 4月7日【新型コロナ】108兆円の緊急経済対策