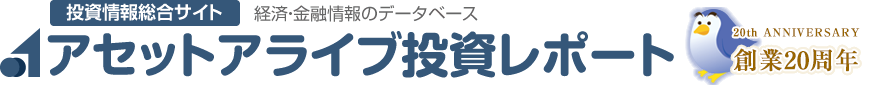九州大学の中島直敏教授らの研究グループは、燃料電池で家庭用に普及が進むタイプの寿命を従来の100倍に延ばせる新技術を開発した。
中核部品に性能の劣化を防ぐ材料を使い、耐久性を大幅に上げた。製造コストも約3割減らせるとしている。2018年の実用化を目指す。
家庭用の燃料電池は、水素と酸素を反応させる「電極触媒」に白金を、反応の家庭で水素イオンを運ぶ「電解質」に水を使うタイプが主流。都市ガスから水素を取り出す際、発生する一酸化炭素が白金を劣化させるため性能が落ちやすかった。
そこで研究グループは、個体の樹脂上にしたリン酸を電解質に使用し、電極触媒にも劣化しにくい新素材を使った。
耐久性試験では、性能を維持できる発電回数が40万回以上と従来の100倍以上になったとしている。
また、電解質の水が蒸発すると機能が失われるため必要だった冷却器も不要になることから、製造コストも減らせるという。
燃料電池車への搭載も目指している。
投資に関する金融市場動向や経済動向のレポートを発信。
- 新着情報
-
- 3月22日【脊髄損傷】
- 5月29日【GDP】各国のGDP推移 2020年
- 5月29日【政策金利推移】2020年
- 5月29日【新型コロナ】第2次補正予算案
- 4月7日【新型コロナ】108兆円の緊急経済対策