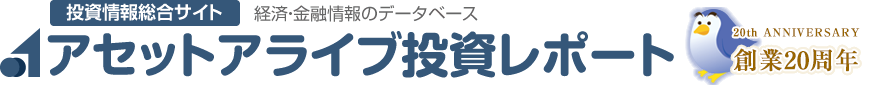厚生労働省の「ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会」は、2013年3月27日、神戸・理化学研究所などが申請したiPS細胞での目の難病「加齢黄斑変性」を治療する臨床研究の審査を始めた。
患者の皮膚からiPS細胞を作る過程などについて理研などに追加データを求め、安全性に関する議論が進められる。
理化学研究所は、2013年2月28日、iPS細胞で世界初の臨床試験実施を申請していた。
{[加齢黄斑変性とiPS細胞を用いた治療法[2082]]}
加齢黄斑変性とは、視覚機能で重要な役割を果たす黄斑部の機能が低下する病気。
視野の中心部でものがゆがんで見えたり、小さく見えたり、暗く見えたり、視力が低下するという症状が起こる。国内の50歳以上の約1%に見られるという。
滲出型加齢黄斑変性は、異常な血管が生じることによる出血で、視覚機能に重要な役割を果たす黄斑部が傷害され、機能が低下することにより視覚障害が起こる。発症原因は特定されておらず、加齢や炎症、遺伝子要因などによる黄斑部の劣化との関連が指摘されているという。
治療のためには、異常な血管を取り除き、傷ついた黄斑部(RPE:網膜色素上皮)を再建する必要がある。しかしながら、RPE細胞の移植は拒絶反応が強く、リスクが高いため日本ではほとんど行われていない。
そこで、患者本人の皮膚細胞からiPS細胞を作製し、RPE細胞を作り出し、シート上にして黄斑部に移植することで、拒絶反応の問題をクリアし、新しい治療法の開発を目指している。
今回、理化学研究所が申請した臨床試験での治療の方法は、患者の上腕部から直径4ミリ程度の皮膚を採取し、iPS細胞を作製し、RPEシートに成長させる。RPEシートが完成するまでに約10ヶ月かかるとしている。
このRPEシートを、以上血管を取り除いた後、黄斑部に移植する。
手術後、1年間は、毎月又は2ヶ月に一度検査が行われる。その後も年に1度、検査が行われ、合計4年間経過観察を行い、安全性や視覚機能への有効性を評価するという。
投資に関する金融市場動向や経済動向のレポートを発信。
- 新着情報
-
- 3月22日【脊髄損傷】
- 5月29日【GDP】各国のGDP推移 2020年
- 5月29日【政策金利推移】2020年
- 5月29日【新型コロナ】第2次補正予算案
- 4月7日【新型コロナ】108兆円の緊急経済対策